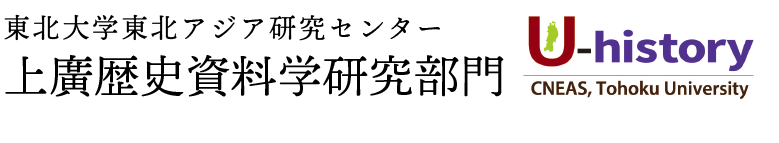コラム:政宗青年期の居城「岩出山城跡」の調査について(佐藤優)
岩出山城跡は、江合川やその支流によって浸食された標高約107mの丘陵上に立地します。本城跡は中世期に大崎氏重臣の氏家氏が代々の居城にした山城で、「岩手沢城」と呼ばれていました。天正19年(1591)の奥州再仕置により伊達政宗は米沢から岩出山に移されます。この時、徳川家康や家臣の榊原康政の手によって城の修築が行われました。以後、10年ほどは政宗の本拠となりますが、慶長6年(1601)に完成していない仙台へ居城を移したといわれます。その後、岩出山城は四男の伊達宗泰に与えられ、明治維新まで存続します。
今回の調査地点は二の丸南東隅に位置し、遺構は堀跡と溝跡等を発見しました。堀跡は二の丸南側の丘陵斜面をほぼ垂直に切り込んだ切岸の下部に掘り込まれています。東西方向に延び、東端部は鉤形に屈曲します。断面の形状は確認できませんでしたが、上幅4.9m以上、下幅1.5m以上、深さ1.5~3.1mです。溝跡は丘陵斜面を南北方向に延び、南端が堀跡と接続します。断面形は逆台形状を呈し、上幅3.0~4.8m、下幅0.5~1.2m、深さ0.8~1.7mです。調査で発見した堀跡は、明暦2年~延宝6年(1656~78)頃とされる「岩出山要害館下絵図」に描かれたものと位置や形状がほぼ同じであることがわかりました。堀跡より出土した遺物から明治期には埋め戻されたものと推測します。次に溝跡の年代は判然としませんが、堀が埋め戻された後も護岸工事を行いながら維持されていたことがわかりました。溝の用途としては二の丸平場の水を流下させる落堀と考えています。
発掘調査では大きな成果が得られましたが、岩出山城跡はほとんどが未調査であることから、これからの調査の進展で新たな発見や見解が期待できます。(大崎市教育委員会文化財課 課長補佐)
(写真)堀跡全景(西から)
(参考)大崎市教育委員会「岩出山城跡ほか」『宮城県大崎市文化財調査報告書第49集』2023年