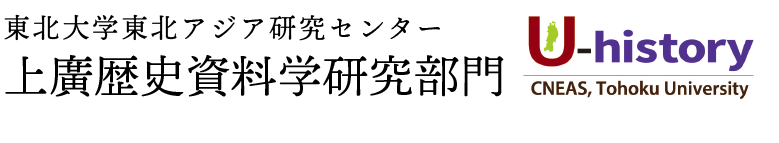コラム:特別展「海に入るまで濁らざりけり-『母なる川』最上川-」について(小嶋康広)
山形県の「母なる川」最上川は、山形県の中央部を流れて酒田から日本海に注ぐ、1つの県のみを流域とする川としては国内で最も長い川です。今から約100年前の大正14年(1925)、皇太子時代の昭和天皇が最上川の情景を詠まれた和歌「広き野をながれゆけども最上川 うみに入るまでにごらざりけり」は、現在「山形県民の歌」として親しまれています。
山形県立博物館では今年「最上川」をテーマとした特別展を開催しています。松尾芭蕉や正岡子規、斎藤茂吉などの歌人が詠んだ最上川を題材とした歌や文学、江戸時代に描かれた川絵図、人々のくらしに関係する資料などを多数展示しています。なかでも、山形県の指定文化財である「松川舟運図屛風」や「羽州川通絵図」、最上川研究の第一人者である柴田謙吾氏が20年もの歳月を費やして描いた40mの川絵図「最上川絵図」などは貴重な資料ですので、この機会に多くの方に見ていただきたいと思います。
今回の展示資料の中で特に注目してほしいのは「2つの『最上川川通絵図』」です。山形市船町の河岸問屋に伝わった「最上川川通絵図」は以前から知られていましたが、近年、この川絵図と全く同じ絵図が大石田町で発見され、山形県博に寄贈されました。江戸時代に河岸(かし)として栄えた2つの町、なぜそこに2つの川絵図が残されたのか。今回初めて一緒に展示しましたので、ぜひ見てほしいと思います。
その他、江戸時代の絵図と現在の航空写真を並べてみることができるデジタルパネルやLEDライトで川の流れを演出したパネル「光流れる最上川」、三難所船下りを紹介するミニシアター「舟でめぐる最上川三難所」、難所を通り抜ける場面をVRで体験できるイベントなど、デジタルコンテンツを活用していろいろな視点から最上川を知ってもらう展示も工夫してみました。今回の展示を通して、最上川の持つ魅力を再認識してもらい、美しい風景を未来につなげていきたいと願っています。(山形県立博物館・学芸員)
(写真)2つの川絵図展示風景