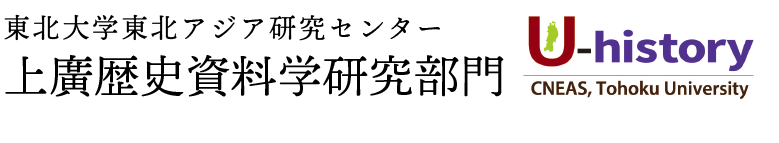コラム:畏れか、崇敬か──歴史が映す鷺の二つの顔(顧婕)
古来より、日本人は動物に特別な力を見いだし、親しみを抱くと同時に畏怖の念を持ってきました。動物の力にあやかろうとしたり、その行動から吉凶を感じ取ったりするなど、動物は日本の精神文化に深く根付いています。その一例として、水鳥の一種である「鷺」(サギ)も特別な意味を持ち、人々に崇敬される存在となってきました。
毎年7月20日と27日に行われる「鷺舞」は、室町時代から伝わる伝統芸能で、舞い手が鷺を模した装束を身にまとい、優雅に舞を奉納する神事です。元々は京都の祇園祭の練り物として登場しましたが、現在では島根県津和野町や京都市の八坂神社での奉納が特に有名です。このように、鷺は神聖視され、信仰の対象となってきました。しかし、それが必ずしも「吉兆と結びつく存在」ではなく、古代の日本では異変や災厄を知らせる不吉な存在とも見なされていました。
『日本文徳天皇実録』仁寿元年(851)3月27日には、鷺に似た鳥が殿前の梅の木に群がる様子が「異変の兆し」として記されています。その後、鷺の群集は占いの対象となり、仁和3年(887)8月12日には、二羽の鷺が朝堂院に集まり、陰陽寮が「火災に注意すべし」と占ったことが確認できます。さらに、承平天慶の乱が勃発した頃、大極殿にも鷺の群れが飛来し、異変が記録されています。これに続いて平将門討伐の命が下されるなど、戦乱の前後に鷺の異変が複数回起こっていることから、当時の人々が鷺を戦乱の予兆と考えていたことが示唆されます。
鎌倉時代に入ると、『吾妻鏡』寛喜2年(1230)6月9日の記録には、鷺の群集を受けて異変を鎮める「鷺祭」が行われたことが記されています。こうした事例からも、当時の人々が鷺の出現を不吉の兆候と見なしていたことがわかります。
しかしながら、鷺が常に不吉の予兆とされたわけではありません。時代が下るにつれ、鷺に対する解釈は多様化し、次第に神聖視される側面が強まっていきます。例えば、『太平記』第39巻「自太元攻日本事」には、蒙古襲来の際に鷺が「神の使い」として崇められ、戦勝を祈願する存在として扱われた記述があります。
このように、鷺の象徴的な意味は、時代や社会の変化に応じて移り変わってきました。その変遷は、単なる吉凶の判断にとどまらず、人々の崇敬や信仰の念が込められてきたことを示しています。自然現象や動物の行動をどのように解釈してきたのかを考える上で、鷺の事例は重要な手がかりとなるでしょう。(東北大学文学研究科博士課程後期・上廣歴史資料学研究部門事務補佐員)
(写真1)単庵筆『鷺図』(1幅、室町時代、東京国立博物館所蔵)
※東京国立博物館「研究情報アーカイブズ」(https://webarchives.tnm.jp/)
(写真2)鷺(韓国・慶州 月城周辺、2024年8月29日、筆者撮影)