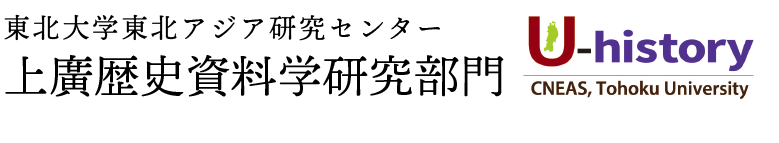コラム:明治時代の感染症隔離施設(竹原万雄)
感染症流行時の有効な対策のひとつに隔離があります。明治時代の隔離施設というと、明治10年代のコレラ流行時の避(ひ)病院に関する研究が多くみられます。避病院は、人家から離れた場所に設けられ、粗末な仮小屋で、患者数に対して医療従事者は足らず、劣悪な環境だったと説明されます。その一方、明治10年代以降のコレラ以外の急性感染症に対する隔離施設の実情はあまり研究されていません。
そのような研究状況のなか、福島県岩瀬郡仁井田村の役場文書には複数の隔離病舎の日誌がのこされています(須賀川市立博物館蔵)。そのうち明治33年(1900)のものをご紹介します。同年は赤痢患者24名が入院し、入院患者が最も多いときは13名にのぼりました。日誌からわかる隔離病舎の部屋は、病室が3室あるほか屍室、消毒室、看護婦室などが確認できます。人員は、事務員1名、予防委員2名に加えて看護婦1名、使丁2名を雇用し、村長や巡査をはじめ県や郡の役人なども監督のため来舎しました。医師は常駐ではありませんが隔日程度で診察に来ていたようです。日誌をみると入院した患者宅にはすぐに消毒に向かい、病舎では汚物・糞便の焼却、病室・便所の消毒などが日常的に行われてました。死者は入院当日に死亡した患者が1名、院内感染はみられませんでした。もっとも、県の検疫官が監視に訪れた際には、便器置場の改良、糞便に汚染した襤褸(らんる・ぼろきれ)は必ず焼却すること、消毒室内に更衣場を設けることなどが注意されており、不十分な点も多々あったようです。
村レベルの隔離施設の様子がわかる本資料はたいへん貴重です。しかし、上記のような隔離施設の状況を評価するには、他との比較が求められます。感染症対策に欠かせない隔離施設がどのように改善されるのか。医療・経済・社会など多角的観点から当時の危機管理能力を考えるテーマといえるのではないでしょうか。
(写真1)隔離病舎日誌の表紙
(写真2)福島県検疫官による注意事項