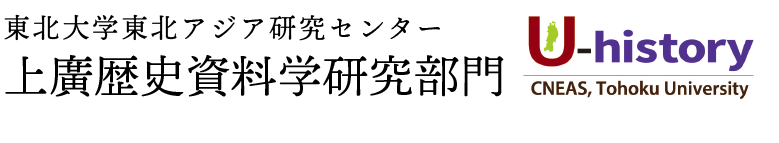コラム:岩出山伊達家家臣が記録したアイヌ民族のクマ送り(菅原慶郎)
いまや、運河とレトロな街並みで名をはせ、国内外からの観光客でにぎわう北海道小樽。150年以上前の明治初年にさかのぼると、北海道方面が新たな日本の領土とされたことで、本州方面から移民たちが到来する玄関口となり、急激に巨大な港町として発展する途上にありました。
そうしたなかに、現在の宮城県大崎市から北海道への移住を決意した岩出山伊達家(伊達政宗の四男を家祖とする)の一団もありました。彼らは紆余曲折を経て、小樽から50キロほど離れた内陸部にあたる現在の石狩郡当別町へと移住する計画を立てました。この中には、家老格である鵙(もず)目貫一郎(1840~1877)なる人物がいました。ところが彼は、病弱を理由に当別へ移住せず、小樽で私塾を開いて、明治6(1873)年の小樽郡教育所設立(小樽で最初の小学校へ)にも関わりました。こうした経緯は、彼が書き遺した10冊ほどの日記から読み取れます。
そこで本題ですが、その一つ「塡(てん)海日記」(当別町教育委員会所蔵、明治5年7月1日から12月28日までの日記)の11月15日条に「此日土人熊送リノ由ニテ観者如織」との記述があります。ここから、鵙目が住む現在の南小樽駅近辺(当時の小樽市街地)でアイヌ民族によって、クマ送り(クマから毛皮などをもらう見返りに、その魂をカムイの世界へと送り返す儀式)が執り行われ、大勢の見物人が集まる様子が見うけられます。わずか15字ほどの記録ですが、おそらく年月日が特定できる小樽で行われた最終年代にあたるクマ送りとみられます。
なぜ最終年代かといえば、小樽のアイヌ民族は、本州方面から移民たちが流入し市街地が急拡大するなか、明治13年頃に郊外の高島(現在の小樽市高島)へ、さらにその後、小樽の眼前に広がる石狩湾をはさんで70キロ以上も離れた地である現在の石狩市浜益(はまます)区へと移住、もしくは離散することになるからです。こうした明治初年における小樽のアイヌ民族の歴史・文化、何よりまもなく直面する大きな苦難の歴史をも見通すうえで、極めて貴重な記録といえます。(東京理科大学教養教育研究院専任講師)
(写真1)「塡海日記」(表紙)当別町教育委員会所蔵
(写真2)「塡海日記」(青丸が引用箇所)当別町教育委員会所蔵