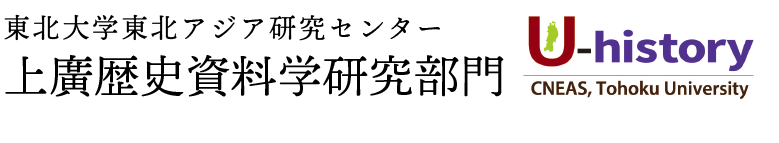コラム:「王道主義」から見る「満洲国」統治:理想・言説・政策の乖離をめぐって(張小栄)
1931年の「九・一八事変」(満洲事変)後、関東軍の主導により樹立された「満洲国」の統治は、複層的な支配構造を特徴とする植民地統治の歴史であったといえます。その重層性は、現地政治空間における複数の勢力が、それぞれの主体性を保持しつつ関与した点において形成されたものと理解できます。建国過程には、現地中国人の文治派・軍閥派・復辟派に加え、現地日本人、関東軍に随伴する植民地統治のイデオローグ、満鉄実務派、教育実務者などが重層的に関わっていました。「王道主義」という統治理念は、これら諸主体の思惑と主体性を集中的に反映した概念として位置づけられます。
「王道主義」は建国期から崩壊に至るまで、「満洲国」の根幹理念として標榜され続けました。それは単なる植民地統治の正当化の標語ではなく、現地住民の主体性を動員し、植民地統治の深層において機能した政治的言説であったと考えます。従来の「脱亜論」や「アジア主義」と異なり、「王道主義」は植民地の現場で生成された支配の政治論理でした。確かにその背景には儒教思想の伝統が認められますが、それは他者性と現地性のはざまで揺れ動きつつ、現地に関与した日本人が主体的に構想した統治理念であったといえます。
この視角において、日本の対外政策に生じた断層を読み解き、「満洲国」の全体像を把握する手がかりが得られます。すなわち、植民地支配の現場における経験として、国づくりに関わった人々の主体性を歴史学的に検討するとき、その輪郭がより明確に浮かび上がると考えます。「王道楽土大満洲国」は、理想であり、言説であり、同時に政策でもありました。「王道主義」における理想・言説・政策の乖離を精査する営為の中に、1930年代に構想された「民族協和」や「王道楽土」の実相を見いだし、「満洲国」の歴史的性格をより的確に把握することができると考えます。(東北大学東北アジア研究センター)
「王道楽土大満洲国」紀念塔は、「満洲国」承認一周年紀念事業として山海関駐屯軍の平田混成旅団が山海関北方一里の角山寺に建設したものであり、1933年10月3日除幕式を行いました。
出典:『満洲国現勢』建国-大同2年度版,満洲国通信社,1933. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1878713 (参照 2026-01-07)