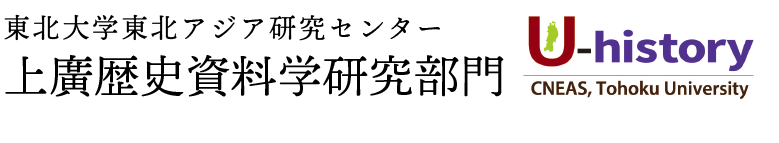コラム:明治初期の開明的行政官 浜田県令 佐藤信寛(矢野健太郎)
明治4年~9年(1871~1876)、当時の島根県は、島根県と浜田県に分かれていました。この時の浜田県の県令(行政のトップ、当初は権令)を務めていたのが、佐藤信寛です。彼は元萩藩士で、農村支配に長じた役人でした。幕末には「幕長戦争」によって、萩藩の占領地となった豊前国企救郡や石見国浜田藩領の代官に就任し、その後、浜田県や島根県の県令を歴任しました。ここでは彼の浜田県時代のエピソードを「浜田県歴史」(各府県の沿革記録【国立公文書館蔵】)から紹介したいと思います。
明治8年2月、佐藤は「地方官会議」の議員が地方長官でありながら「人民代議士」を称する事は「名實相背キ」という状況にあるとして、各県下の人民からも代議士を選出する事を太政大臣に建白したとあります。
さらに同年6月には、当時の地方行官が判事を兼任している状況に対して、その兼任の停止、大審院(現在の最高裁判所)および各地に裁判所の設置(当時は各県において状況がまちまちであったようです)などの司法制度についても建白をしています。当然ながら、この建白は「三権分立」の思想に基づくもので、建白の冒頭においても「制法・政令・司法ノ三体併立、互ニ勢ヲ均シ、彼此相控制シテ、其偏頗ヲ防ク、故ニ国家ノ品序秩然トシテ、上下通暢シ長ク安寧洪福ヲ得セシム、是ヲ立憲政体ト云フ」と述べています。モンテスキューの『法の精神』の翻訳『万法精理』(何礼之【がのりゆき】訳)の出版が同年5月であったことからすると、かなり早い段階でこうした情報にも触れていたのかもしれません。
このように佐藤は、非常に開明的な明治初期の行政官のひとりだったと言えるのではないでしょうか。そして、彼の子孫からは、佐藤栄作、岸信介、安倍晋三という3人もの総理大臣が輩出されたということも特筆すべき事かもしれません。(島根県古代文化センター)
明治8年2月 地方官会議議員に関する建白(「浜田県歴史 政治部(明治8・9年)」、国立公文書館所蔵)
明治8年6月 司法制度に関する建白(「浜田県歴史 政治部(明治8・9年)」、国立公文書館所蔵)