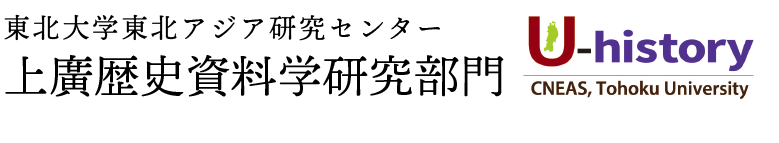コラム:長野県旧木曾山林学校の歩み―林業専修教育の模索と格闘―(青木健)
コロナ禍をきっかけに、自らの研究の幅や視点を広げようと思い立ち、林業と森林経営に関連した専門人材の育成に特化した歴史も調べ始めました。Web検索作業で出会ったのが、長野県の木曾山林資料館が運営する「校友會報アーカイブ」(http://kisosanrin1901.org/木曽山林学校デジタルアーカイブ/)です。これをきっかけに同校の学校史とその校友ネットワークの研究に着手しました。
木曾山林学校は、1899(明治32)年公布の実業学校令にもとづいて、長野県西筑摩郡に設立された林業専修の中等学校です。教授科目の大半は、植物学や森林経理学をはじめとする森林管理のための専門科目で、林務行政の実務経験者を含む教諭達によって教育が行われました。帝室林野が広がる木曾谷で同校が開校された背景のひとつには、科学的な人工造林技術を青少年に習得させたいという地元住民の熱意がありました。学校の立地上、寄宿代も含めた修学費用は高額でしたが、生徒募集は好調で全国から志願者が集まりました。
開校した木曾山林学校にとっての難題は卒業生の就職先を開拓することでした。木曾谷では、同校の卒業生が希望する専門職の雇用は、帝室林野管理局の地元出先機関にほぼ限られたためです。そのため、同校の校長や教頭は日本各地や植民地の林務関係の官公庁、そして林業部門をもつ財閥系大企業等からの求人を開拓していきました。
林務行政の現場に輩出された木曾山林学校の卒業生の多くは、森林管理や地域林業の最前線のポストに配置されました。現在、その現場に巣立った同校OB達の校友ネットワークの実態や、各地の林政・林業におけるその役割について重点的に研究を続けています。 (成城大学経済学部 准教授)
西筑摩郡福島町にあった創立当時の木曾山林学校(写真:木曾山林資料館 提供)