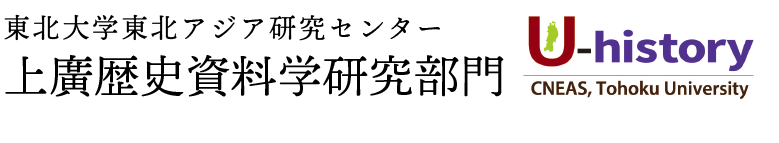コラム:漱石の主治医・森成麟造と考古学そして東北大学 (柳原敏昭)
1910年8月、静岡県修善寺温泉に療養中の夏目漱石(1867―1916)は大量吐血し、しばらく生死の境をさまよいます。文学史上、「修善寺の大患」と呼ばれるできごとです。このとき治療に当たったのが森成麟造(もりなりりんぞう)(1884―1955)という青年医師です。森成は東北大学の前身校のひとつ仙台医学専門学校の出身で、「大患」直前に漱石が入院していた東京の長与胃腸病院の勤務医でした。治療の甲斐あって、漱石は一命を取り留めます。修善寺での森成の奮闘ぶりは、小宮豊隆「修善寺日記」などに記されているところです。小宮豊隆(1884―1966)は漱石門下の筆頭格で、後に東北帝国大学法文学部の教授となり、ドイツ文学を講じました。東北大学が誇る「漱石文庫」は、小宮の附属図書館長時代に受け入れたものです(1943・44年搬入)。
森成はその後、郷里に程近い新潟県高田市(現上越市)で開業することになります。漱石は、東京を去る森成のために自邸で送別会を開いています。その折の漱石の家族と門下生がずらりと並んだ記念写真も残っています。両者の親交は続き、漱石が森成の招きで高田市を訪問したこともあります。以上述べたようなことをテーマとして、2023年春から夏にかけて、新宿区立漱石山房記念館では、テーマ展示「漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造」を行っています。
郷里における森成は、医師であるとともに地方文化人として様々な顔を持っていました。そのひとつが考古学愛好者、考古遺物コレクターとしての顔です。推されて、上越考古学会の会長にも就いています。
その森成のコレクションや上越考古学会に熱いまなざしを注いでいた東北帝国大学の教員がいました。法文学部国史研究室(現文学研究科日本史研究室)の喜田貞吉(1871―1939)です。喜田は古代史と考古学が専門で、1925年に奥羽史料調査部(文学研究科東北文化研究室の前身)を立ち上げ、東北地方および北海道・新潟県を範囲として調査・研究を進めていました。喜田は何度か森成の自宅を訪ね、考古遺物を見学したり、共に周辺の遺跡の調査に出向いたりしています。調査の合間には、仙台や漱石・小宮のことも話題にしていたに違いありません。森成については東北地方に愛着をもっていたという証言もあります(「森成先生の思い出を語る座談会」、『頸城文化』8、1955年)。森成のコレクションは現在、上越市立歴史博物館に収蔵され、2022年夏には企画展「森成麟造―上越考古学の先覚者―」が開催されました。
このように森成麟造という人物に注目すると、夏目漱石、小宮豊隆、喜田貞吉といった人々をつなぐ糸が絡み合い、東北大学とも結びついていたことが見えてきます。人の縁とは不思議なものです。蛇足ながら、筆者は森成が出た高校(当時は旧制中学校)の卒業生です。 (東北大学大学院文学研究科)
*参考文献:企画展図録『森成麟造―上越考古学の先覚者―』(上越市立歴史博物館、2022年)。
上越市立歴史博物館の企画展図録『森成麟造―上越考古学の先覚者―』表紙。写っている人物が森成麟造。掲載にあたっては同館の了解を得た。