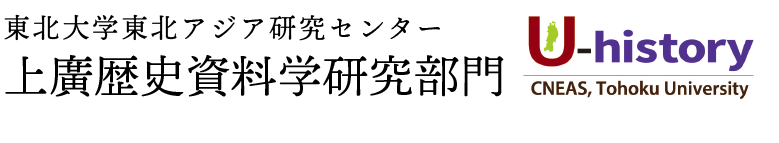コラム:道山三次郎の研究から地方名望家研究の可能性を考える(伴野文亮)
皆さんは、道山三次郎という人物をご存じでしょうか。
三次郎(1833-1900)は陸奥国須賀川(現在の福島県須賀川市)に生れ、明治期の須賀川にあって地方名望家として地域の「近代」化に尽力した人物です。また「壮山」という俳号をもち、近世から俳諧が盛んに行われていた同地にあって、いわゆる「旧派」の俳人としても活躍しました。
俳人としての三次郎の姿は、様々な資料からうかがうことができます。例えば、松尾芭蕉の没後200回忌を記念して彼が編者となって制作された『早苗のみけ』(1893年)という本が挙げられます。同書は、須賀川市立図書館や名古屋市博物館など、全国各地の資料所蔵機関に所蔵が確認されていますが、富山県立図書館所蔵本には同書を包んでいた袋も一緒に遺されています。その袋には、書名が書かれた表面の反対側(裏面)に「文音所/岩代国岩瀬郡須賀川町/道山三次郎」とあり、同書の制作過程で三次郎が句を集約する窓口となっていたことが分かります。この袋は、それ自体が残ることも稀ですが、三次郎と壮山が同一人物であることを端的に示している点でも大変興味深い歴史資料であるといえます。
三次郎をめぐっては、俳人「壮山」としての姿や力量はこれまでも言及されることがあった一方で、名望家としての三次郎の姿は未だ十分には捉えられていません。今後は、地域の内外に遺る多様な歴史資料を手掛かりとして、近世・近代転換期の須賀川を生きた道山三次郎の姿を総合的に検討してく必要があります。その際には、安積疎水の完成に尽力し、須賀川市内にある神炊館神社に辞世の句を彫った句碑と顕彰碑が建つ小林久敬(1821-1891)など、三次郎と同時代を生きた他の名望家との比較も重要なポイントになるでしょう。地方名望家たちの文芸実践に着目することで、従来の枠組みとは異なる名望家研究のアプローチが実現できるはずです。
(鹿児島大学法文学部「鹿児島の近現代」教育研究センター特任准教授)
(写真1)神炊館神社に建つ小林久敬の辞世の句碑と顕彰碑