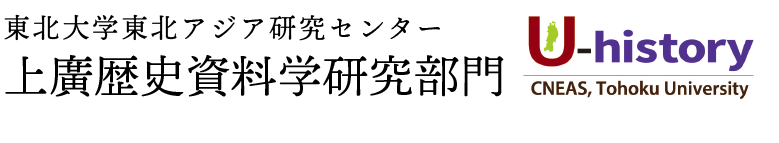コラム:東北大学考古学研究室所蔵 多賀城廃寺出土塑像片の調査(堀裕)
思わぬ機会に、東北大学考古学研究室の収蔵庫に入ることができたのは、2017年のことだったと記憶します。視線を右左へと送りながら庫内を巡り歩いていると、年代物の木箱と、その中にビニール袋に小分けされた土塊に目がとまりました。その木箱と袋には、多賀城に隣接する多賀城廃寺出土の塑像片であることが注記されており、どうやら1960年代に伊東信雄氏等が行った発掘調査当時の姿を留めているようなのです。
これより以前、私は、上廣歴史資料学研究部門が共催する講座で、多賀城廃寺について話をさせていただき、それを論文にまとめていました。その準備のため、多賀城跡調査研究所所蔵の多賀城廃寺出土の塑像片を調査していたのです。その時は気づかなかったのですが、伊東氏の調査資料は、研究所だけでなく、東北大学にも納められていたのでした。
昨年、調査について鹿又喜隆氏(東北大学)に相談したところ、望外にも考古学実習の一部をその整理作業に充てていただき、鹿又氏と考古学研究室の学生を中心に、私や日本史研究室の院生も加わった整理作業が始まりました。整理が進むにつれ、表面に細かな粒子の粘土層を持つ少数の塑像片のほかに、作りが比較的単純な大量の土塊があることが分かり、土塊には、平坦な面や、内部の木組みの跡、何かが塗られた痕跡などあることが明らかになってきたのです。昨夏、鹿又氏の尽力により、共同で群馬県山王廃寺出土塑像の調査ができた時の成果や、偶然目にした平泉世界遺産ガイダンスセンターと瑞巌寺宝物館の展示資料から、土塊は多賀城廃寺の土壁であることが明確になってきました。
調査課題をひとつ付け加えるならば、期待していた塑像片は思いのほか少なく、顔など主要な部分は、大学にも多賀城跡調査研究所にも見当たりません。多賀城廃寺は、建物が焼けて倒壊した状態のまま出土した遺物もあると考えられているのですが、塑像片に限っていえば、主なものは拾われるなど、なんらかの取捨選択を受けたと推測されるのです。これらの調査成果については、後日公表したいと考えています。
(東北大学大学院文学研究科)
(謝辞)これまでの調査・研究にあたっては、上記のほか、荒武賢一朗氏、高橋栄一氏、長岡龍作氏、新野一浩氏、羽柴直人氏、初野野博之氏、前原豊氏、八重樫忠郎氏、吉野武氏等のご協力とご教示をいただきました(五十音順)。
(参考)拙稿「多賀城廃寺―尊像と塔から―」(『東北アジアセンター研究報告』第10号、2013)は、下記URLに掲載しています。
https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=51290&item_no=1&page_id=33&block_id=46